技術・適用情報
軽量盛土 カルグリ
軽量盛土材 カルグリの概要
1.概要
カルグリは軽量コンクリート用に開発された人工軽量骨材を盛土・裏込め用に0~40mmの範囲で粒度調整したものである(写真1)。転圧後の密度は12kN/m³程度で、天然土質の16~19kN/m³などに比べて軽く、内部摩擦角も42度が得られる。千葉県鋸南町産の膨張性頁岩に加え、首都圏自治体から発生する下水処理場汚泥焼却灰、浄水場汚泥などを原料としている。原料は混合、造粒された後1,100℃で焼成しており、有害物質の発生や溶出はなく、環境省の土壌環境基準をクリアしている。

●写真1 カルグリ外観
2.特徴
- EPS工法やFCB工法と比較して施工が容易。
- 粒密度が1以上のため、浮き上がりや流失の恐れがなく、水中施工が可能。
- 透水性が良好でそれ自体が排水層として機能する。
- 擁壁背面の裏込めに使用した場合、擁壁基礎巾を小さくできる。
- 締固め特性は含水比に左右されず、雨天での施工可能。表1にカルグリの物性を示す。
■表1 カルグリ物性(例)
| 密度(転圧後)(kN/m³) | 11.6 | ||
|---|---|---|---|
| 最大乾燥密度(kN/m³) | 9.67 | ||
| 内部摩擦角(度)(Dr=60%) | 42.2 | ||
| 95%修正CBR(%) | 21.6 | ||
| 透水係数(cm/sec) | 1.05 | ||
| 粒度(通過率%) | 40mm | 20mm | 5mm |
| 98~100 | 80~95 | 20~50 | |
3.施工方法
カルグリの施工は原則として小型の転圧機械を用いて行う。その他は一般的なクラッシャランと同様な施工を行えばよく、適用部位により撒き出し厚を変える。施工方法と得られる物性を表2に示す。
■表2 施工方法と得られる物性
| 適用部位 | 路 床 | |
|---|---|---|
| 施工機械 | 振動プレート | 2.5tローラー |
| 転圧回数 | 6 | 10 |
| 撤出し厚(cm) | 22 | |
| 密度(転圧後)(kN/m³) | 12 | |
4.適用範囲
- 軟弱地盤上の盛土の沈下低減(海上埋立、道路、防波堤)
- 埋設物への土圧低減及び不同沈下対策(地下駐車場、沈埋トンネル)
- 擁壁背面の土圧及び地盤反力の低減
- 傾斜地での盛土や矢板護岸における土圧低減及び地すべり防止
5.施工例
- 1.既設護岸の裏込め
- 既存護岸への土圧軽減と護岸背面沈下抑制を目的として、各種軽量盛土工法が検討された。しかしながら、施工数量が450m³程度であったため、EPS工法や、SGM工法では施工手間が過大になると予測された。また、コスト面では各工法とも有意差が認められなかったため、施工性を考慮した場合、カルグリが最も簡便であると判定された。
- (図1、写真2,3)
- 2.道路拡幅工事(水中盛土)
- 河川沿道の拡幅工事において、鋼管矢板への土圧軽減及び滑動防止を目的として各種軽量盛土工法が検討された。ここでは、水中盛土が大部分を占めるため、水による浮き上がりがないもの、さらに河川への有害物質の流出を起こさないものとしてカルグリが採用された。
- (図2、写真4)
- 3.下水処理場覆蓋上の緑地公園化
- 首都圏の浄水場では、市民への開放を目的に覆蓋上を緑地公園化するケースがしばしば見られる。既存スラブへの荷重には制限があり、材料に軽量なものが求められる。ここでは排水層としてスラブ上全面にメサライト粗骨材が、管理用道路の路床としてカルグリが採用された。
- (図3、写真5,6)
- 4.傾斜地の地盤
- 傾斜地に建つ住宅はコンクリート擁壁やブロックで水平な地盤面を確保するケースが多々見られる。埋め戻し材にカルグリを使用することによって擁壁への負担軽減、不同沈下の防止、ならびに耐震性の向上、さらに盛土地盤の排水性向上が期待できる。
- (図4、写真7)
- 5.ホームのかさ上げ
- 高齢者や身障者の乗降を容易にするため、ホームと列車の段差を解消する工事が各地で行われている。しかしながら高架ホームの場合、上載荷重に制限がある。このため、軽量なものが求められ、カルグリが採用された。また、転圧後、直にアスファルト舗装行うことや、施工厚さが15cm程度と薄いため、粒度を0~20mm(5mm以下を60%)に調整したものを使用した。
- (図5、写真8)
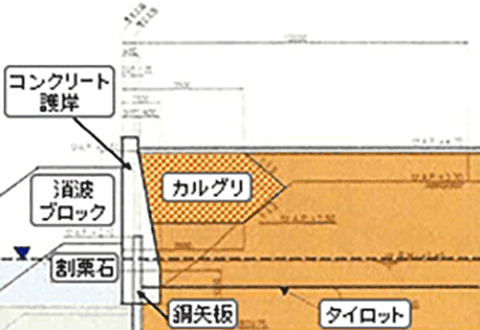
●図1 護岸の裏込め(断面)

●写真2 護岸の裏込め(ブルによる撒出し)

●写真3 護岸裏込め(ローラーによる転圧)
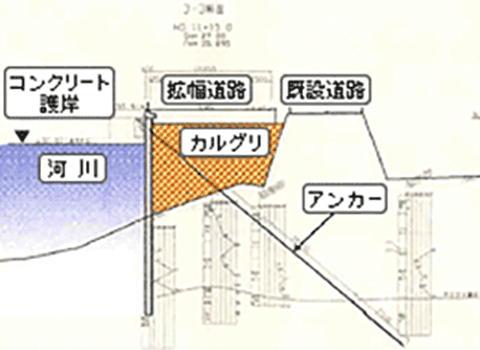
●図2 道路拡幅工事(断面)

●写真4 道路拡幅工事(水中盛土部分撒出し)
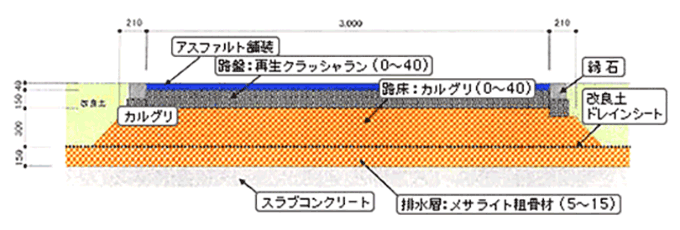
●図3 緑地公園化工事(断面)

●写真5 緑地公園化工事(覆蓋スラブ全景)

●写真6 緑地公園化工事(路床部分転圧状況)

●写真7 傾斜地の地盤
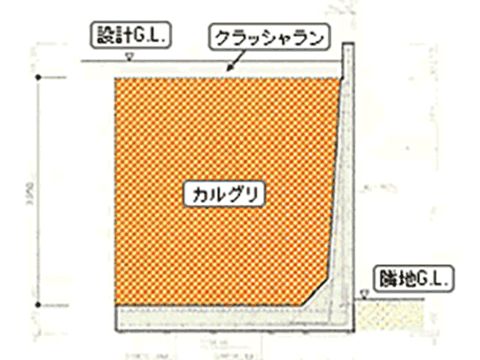
●図4 傾斜地の地盤(断面)
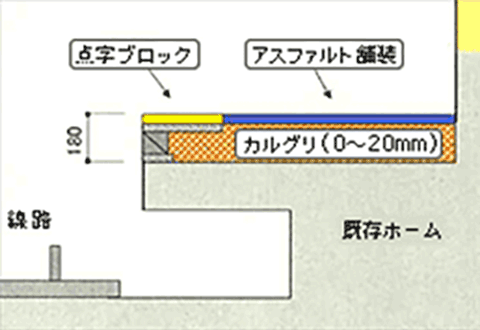
●図5 ホームかさ上げ(断面)

●写真8 ホームかさ上げ(施工途中)
6.まとめ
コンクリート用人工軽量骨材の盛土材としての使用実績は、わが国でも昭和40年代はじめごろから年に数件あったものの、特にPRしてこなかったせいもあり、年間使用量は欧米に比べはるかに少ない量に留まっている。
カルグリも平成13年に国土交通省新技術情報提供システム(NETIS)登録したのを機に採用実績が徐々に増えてきており、今後さらに幅広い用途に対応できるよう改良を実施していく予定である。